空き家の草刈りを放置するリスクと対策
- 黒木開発
- 9月26日
- 読了時間: 16分
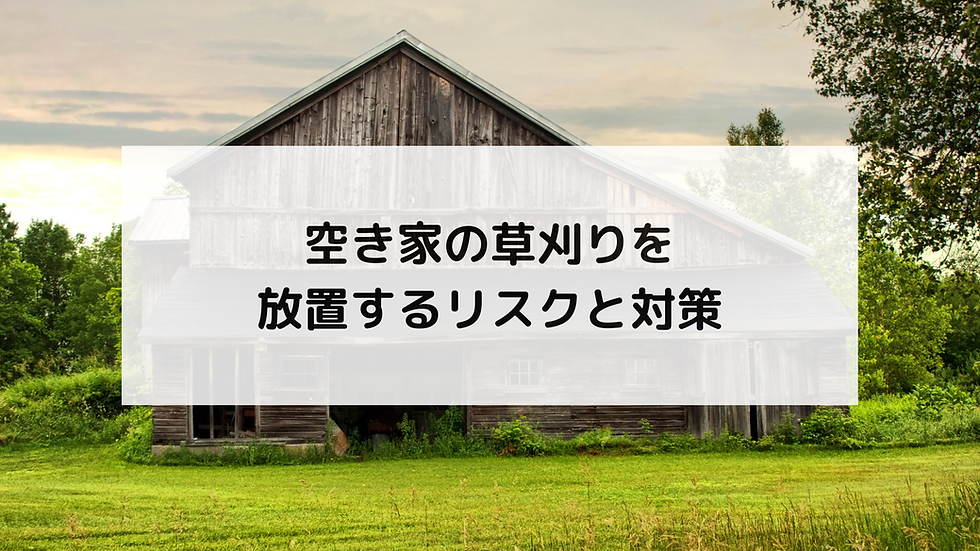
▶︎1. 空き家を放置して草刈りを怠るとどうなる?

1.1 空き家管理に草刈りが欠かせない理由
空き家を所有していると、思った以上に管理の手間がかかります。その中でも特に重要なのが草刈りを定期的に行うことです。雑草は放置しているとあっという間に伸び、空き家全体の環境に悪影響を与えてしまいます。
まず、雑草は日当たりや雨の条件がそろうとわずか数週間で膝丈ほどに成長します。短期間の放置でも見た目が大きく変わり、管理不足の印象を与えてしまいます。見た目の悪化は資産価値を下げる要因にもなるため、早めの対応が欠かせません。
さらに、雑草は根を広げることで地面の通気性や排水性を悪化させます。湿気をため込みやすくなり、建物の基礎や外壁にダメージが及ぶ可能性もあります。小さな草の放置が、結果的に大きな修繕費用につながることも少なくありません。
よくある失敗としては、
夏だけ草刈りをして春や秋を見落とす
庭先だけ整え、家の裏側を放置する
一度にまとめて作業しようとし、結局手が回らなくなる といったケースが多いです。
解決策としては、年に数回の定期スケジュールを組むことが効果的です。特に成長が早い梅雨から夏にかけて重点的に草刈りを行い、春と秋に補助的な管理を取り入れると、空き家全体の環境を良好に保てます。
空き家を健全に維持するためには、草刈りは基本中の基本の管理作業です。
1.2 草刈りを後回しにする一般的な背景
空き家の草刈りが必要だと分かっていても、つい後回しになってしまうことは多いです。理由のひとつは、空き家が普段の生活圏から離れていることです。遠方にあると足を運ぶのが面倒になり、気づいたら草が伸び放題になっている、という状況に陥りやすいです。
また、草刈りは肉体的な負担が大きい作業でもあります。特に夏場は気温が高く、熱中症のリスクを伴うため「今度にしよう」と先延ばししがちです。加えて、必要な道具を揃えたり、刈った草を処分したりと、実際にやるとなると作業工程が多く、腰が重くなるのも一般的な理由です。
よくある失敗には以下のようなものがあります。
予定を立てずに「気が向いたらやろう」と思って放置してしまう
草刈り機や道具を持っていないため、結局行動に移せない
作業を一人でやろうとし、体力的に限界を感じて中途半端になる
こうした失敗を避けるには、あらかじめ作業スケジュールを決めておくことが大事です。例えば「梅雨入り前に1回、夏の終わりに1回」といったように目安を決めておくと、無理なく継続できます。また、道具をレンタルしたり業者に依頼したりする方法を取り入れると、負担を減らしつつ確実に草刈りを実行できます。
草刈りを後回しにしないためには、負担を分散し、実行しやすい仕組みを作ることが大切です。
1.3 草の成長スピードが放置リスクを高める
雑草の成長スピードは想像以上に早く、放置リスクを一気に高めます。特に梅雨から夏にかけては、雨と日差しがそろうことで草の勢いが増し、数週間で腰丈にまで伸びてしまうこともあります。気づいたときには、人が立ち入るのも大変なほど密集していることも少なくありません。
草が伸びすぎると、単なる景観の悪化だけでなく、害虫や害獣の住みかになったり、湿気がこもって建物の劣化を早めたりします。また、伸びた草は刈る量が増えるため、労力もコストも一気に跳ね上がります。後回しにすればするほど、草刈りが難しくなるのが現実です。
よくある失敗としては、
「数週間くらいなら大丈夫」と油断する
草丈が低いうちは見過ごし、気づいたときには大掛かりな作業が必要になる
草が伸びきってから一気に刈ろうとして体力的に続かない
解決策は、草が短いうちからこまめに対処することです。膝丈以下であれば作業が楽で、処分量も少なくて済みます。また、除草剤や防草シートを組み合わせると、次の成長を遅らせることができ、管理の手間が大幅に減ります。
雑草は短期間で一気に成長するため、早めの草刈りが結果的に時間も費用も節約につながります。
▶︎2. 空き家で草刈りを放置するリスクとその影響

2.1 近隣トラブルや景観悪化につながる
空き家の草刈りを放置すると、まず問題になるのが近隣への迷惑と景観の悪化です。雑草や木の枝が伸びると、隣地に越境してしまうことがあります。道路や歩道にはみ出すと通行の妨げにもなり、クレームやトラブルの原因になりやすいです。
また、雑草だらけの空き家は見た目の印象が大きく下がります。住宅街に一軒だけ荒れた家があると、周囲の雰囲気まで悪く見えてしまいます。地域の人から「管理されていない家」と思われると、防犯面でも狙われやすくなるため注意が必要です。
よくある失敗としては、
表側だけ刈って、裏庭や道路側を放置してしまう
年に一度の草刈りで十分と考え、夏の急成長を見落とす
景観への影響を軽視して、苦情が来てから慌てて対応する
これを防ぐには、敷地の全体を均等に管理することが大事です。特に道路や隣地と接する部分は目立ちやすいため、重点的に手入れすると安心です。
景観の悪化は近隣関係の悪化にも直結するため、草刈りを怠らないことが信頼を守る第一歩です。
2.2 害虫や害獣の発生による被害
雑草が伸び放題の空き家は、害虫や害獣の温床になりやすい環境です。夏場は蚊やハチが繁殖しやすく、草の密集した場所は格好のすみかになります。秋以降はネズミや野良猫が入り込み、場合によっては建物内部に侵入することもあります。
こうした被害は、空き家だけでなく周囲の住宅にも悪影響を与えるため非常に厄介です。
特に多い失敗は次の3つです。
虫が少し出始めても「そのうち減るだろう」と楽観視して放置する
草刈りをしても刈った草をそのまま残し、害虫の温床を作ってしまう
裏庭や建物の陰など目に入りにくい場所の草を放置する
これを防ぐためには、刈った草を速やかに処分することが欠かせません。放置すれば、雑草は乾燥して害虫や小動物の隠れ場所になります。また、定期的に除草剤を使用したり、防草シートを敷いたりして、雑草の発生自体を抑えることも有効です。
害虫や害獣の被害を防ぐためには、草刈りと草の処分をセットで行うことが大切です。
2.3 防犯や資産価値の低下につながる
雑草や木が伸び放題の空き家は、防犯面で非常にリスクが高まります。草木が建物を覆うようになると外からの視界が遮られ、空き家かどうかが分かりにくくなります。その結果、不法投棄や不審者の侵入、放火といった犯罪のターゲットになりやすくなります。
さらに、外観の荒れた空き家は資産価値の低下を招きます。売却や賃貸を検討する際に「管理されていない物件」と見なされ、査定額が下がる原因になることも少なくありません。近隣の住民からも「治安が悪く見える」と敬遠されることがあり、周辺環境全体の価値にも影響します。
よくある失敗は次の3つです。
建物内部の状態ばかり気にして外回りを後回しにする
「売るときに整えればいい」と考えて長期間放置する
人目につきにくい部分の草刈りを軽視してしまう
防犯と資産価値を守るためには、外から見える部分の草刈りを定期的に行い、管理されている印象を維持することが不可欠です。「見た目を整えること」が、そのままリスク回避につながります。
▶︎3. 空き家の草刈りを放置する場合の被害事例

3.1 近隣住民とのトラブルが発生するケース
空き家の草刈りを怠ると、まず問題になるのが近隣住民とのトラブルです。雑草や木の枝が伸びて隣の敷地に侵入すると、庭の景観を損ねたり、車の出入りを妨げたりする原因になります。
特に夏場は雑草の成長が早く、数週間放置するだけで越境してしまうことも珍しくありません。
ありがちな失敗は次の3つです。
自分の土地だから問題ないと思い、越境していることに気づかない
「次に来たときにまとめてやろう」と考えて先延ばしにする
苦情が出てから慌てて対応し、関係性が悪化する
一度でもトラブルになると、「管理を怠っている人」という印象が強まり、信頼回復には時間がかかります。地域での暮らしや資産価値に影響を与えることもあるため、軽く考えてはいけません。
解決策は、定期的に現地を確認し、隣地や道路との境界部分を優先して草刈りすることです。とくに道路沿いや隣接地は目立ちやすいため、短いサイクルでチェックするのが安心です。
近隣トラブルは一度起こると長引きやすいため、予防のための草刈りが欠かせません。
3.2 行政から指導や措置を受けるケース
空き家の草刈りを長期間放置すると、行政から指導や措置を受ける可能性があります。雑草や樹木が道路にはみ出したり、防災や衛生上の危険があると判断された場合、自治体から「草を刈るように」といった文書が届くことがあります。
さらに、改善されない状態が続くと「特定空家」に指定されるリスクがあります。特定空家に認定されると固定資産税の優遇が外れるうえ、行政代執行で強制的に草刈りや撤去が行われ、その費用が所有者に請求されます。
よくある失敗は次の3つです。
注意文書が届いても「すぐにやらなくてもいいだろう」と放置する
草刈りを一度だけして、その後の管理を怠る
現地を確認せず、行政からの連絡で初めて状況を知る
これを防ぐためには、定期的に現地確認を行い、早めに草刈りをしておくことが重要です。もし自分で管理できない場合は、専門業者に依頼して「管理している状態」を維持することが、行政からの指導を避ける近道になります。
行政からの措置は費用や手間が一気に大きくなるため、放置する前に対策を取ることが大切です。
3.3 草刈り放置で修繕費が高額になるケース
草刈りを怠ると、見た目や近隣への影響だけでなく、建物そのものに被害が及びます。雑草が地面を覆うことで湿気がこもり、基礎部分や外壁の劣化を早めてしまうことがあります。
また、ツル性の植物が壁や屋根に絡みつくと、外壁材を傷めたり雨どいを詰まらせたりする原因になります。
こうした状況を長期間放置すると、外壁の補修や雨どいの交換といった大規模な修繕が必要になり、結果的に数十万円以上の費用がかかるケースも珍しくありません。つまり、数千円で済む草刈りを怠ったことで、修繕費が一気に跳ね上がる可能性があるのです。
よくある失敗は次の3つです。
「建物内部に影響はない」と思い込み、外回りの草を軽視する
雑草が外壁や屋根に絡みついても気にせず放置する
小さな劣化を見過ごし、気づいたときには修繕が大規模になっている
解決策は、草が建物に触れる前に定期的に刈り取ることです。外壁や雨どいの周辺は特に注意が必要で、早めに対処すれば修繕費用を大幅に抑えられます。
草刈りを放置すれば、わずかな管理不足が大きな修繕費につながる危険があります。
▶︎4. 空き家の草刈り放置を防ぐ具体的な対策
4.1 定期的な草刈りでリスクを回避する
空き家の草刈りを効果的に行うには、定期的なスケジュールを立てて実行することが大切です。雑草は春から秋にかけて成長が早く、特に梅雨から夏にかけては数週間で一気に伸びます。この時期を中心に、年に2〜3回は草刈りをするのが理想的です。
例えば次のようなタイミングが一般的です。
5〜6月:梅雨入り前に一度刈り、成長期の草を抑える
8月:真夏のピークに合わせて再度刈る
10〜11月:冬前に整えて、翌春の雑草発生を軽減する
よくある失敗には、
夏だけに集中して草刈りを行い、春や秋を忘れてしまう
予定を決めずに「気が向いたらやる」スタイルで結局放置する
草丈が高くなってからまとめて刈り、大量の処分に苦労する
これを防ぐには、カレンダーに予定を書き込み、「草が伸びる前に刈る」習慣をつけることが効果的です。短い草なら作業時間は半分程度で済み、体力的な負担も大幅に軽減できます。
定期的な草刈りは、近隣トラブルや修繕費の増大を防ぐ最もシンプルで確実な方法です。
4.2 自分で草刈りする場合と業者に依頼する場合の違い
空き家の草刈りは「自分でやるか」「業者に依頼するか」で大きく違いがあります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、状況に合わせて選ぶことが大事です。
まず、自分で草刈りをする場合は費用を抑えられるのが最大のメリットです。必要なのは草刈り機や鎌などの道具代と処分費用だけです。ただし、作業には体力が必要で、特に夏場は熱中症の危険もあります。また、遠方の空き家だと移動時間や道具の持ち運びが負担になります。
一方、業者に依頼する場合は短時間で仕上がりがきれいになるのが魅力です。草刈りから草の処分まで一括で対応してもらえるため、手間を大幅に減らせます。その分、費用はかかりますが、自分で行うと数日かかる作業が数時間で終わるケースもあります。
よくある失敗には、
「自分でやれば無料」と考えて道具代や処分費を見落とす
作業中にケガをして医療費や時間的損失が大きくなる
安さだけで業者を選び、仕上がりや対応に不満が残る
解決策としては、作業量や自分の体力、空き家との距離を考えて現実的な方法を選ぶことです。時間や安全性を重視するなら業者依頼、コストを優先するなら自力での草刈り、と状況に合わせて判断するのがおすすめです。
草刈りは「安く済ませたい」か「早く確実に終わらせたい」かで最適な方法が変わります。
4.3 草刈り後にできる予防策(防草シートや除草剤など)
草刈りをした直後はきれいに見えても、雑草は時間が経てばまた伸びてきます。そこで大切なのが、草刈り後の予防策を組み合わせて再発を防ぐことです。
代表的な方法は次の3つです。
防草シートを敷く
地面にシートを張ることで光を遮り、雑草の発生を大幅に減らせます。敷き詰める手間はありますが、一度施工すると数年間効果が持続するのがメリットです。
砂利を敷き詰める
防草シートと組み合わせるとさらに効果的です。見た目も整い、歩くと音が出るため防犯面でもプラスになります。
除草剤を使う
即効性が高く、広い範囲でも効率的に雑草を抑えられます。ただし種類によっては効果の持続が短い場合があり、人体や環境への影響にも注意が必要です。
よくある失敗には、
草刈り後に何もしないため、すぐに雑草が再び繁殖する
防草シートを部分的にしか敷かず、隙間から草が生えてしまう
除草剤を一度だけ使用して、継続管理を怠る
これを防ぐには、複数の方法を組み合わせて管理することがポイントです。たとえば防草シートと砂利を併用すれば見た目も良く、雑草の発生も大幅に減らせます。
草刈り後のひと工夫で、次の管理がぐっと楽になります。
▶︎5. 黒木開発の草刈り・伐採サービスで安心管理
5.1 提供しているサービス内容と強み
黒木開発は、除草や伐採を専門に行う地域密着の業者です。現地の状況に合わせて最適な方法を提案できるため、無駄のない作業と丁寧な仕上がりを両立しています。
主なサービス内容と強みは以下の通りです。
機械作業と手作業の両方に対応
広い土地はスピーディーに機械で、狭い場所や細部は丁寧に手作業で対応可能。
少数精鋭で無駄のない作業
人数を絞った効率的な体制により、余計な人件費をかけず、スピードとコストを両立。
幅広い業務内容
草刈りだけでなく、伐採や刈り倒しにも対応。空き家や空き地の環境を総合的に整備できる。
仕上がりの丁寧さを重視
ただ早いだけでなく、仕上がりの美しさや安全性にもこだわっている。
こうした特徴から、草刈りから木の処理まで安心して任せられる存在として、多くの人に選ばれています。
黒木開発の魅力は、スピード・丁寧さ・柔軟さを兼ね備えたバランスの良い対応力にあります。
5.2 利用しやすい料金体系と作業の流れ
黒木開発のサービスは、料金が分かりやすく設定されているため、初めて依頼する人でも安心です。作業の流れもシンプルで、見積もりから施工までスムーズに進められます。
主な料金体系
機械除草:10㎡あたり 2,000円〜
手作業除草:10㎡あたり 5,000円〜
伐採(高さ3m未満の木):1本 10,000円〜
刈り倒しのみ:要相談
※草刈りから処分まで対応可能で、追加料金の不安を抑えられるのがポイントです。
作業の流れ
問い合わせ・無料見積もり
話やメールで相談可能。現地の状況を確認して見積もりを提示。
作業プランの提案
機械と手作業を組み合わせ、最適な方法を提案。
施工開始
効率的に草刈りや伐採を実施し、丁寧に仕上げる。
後処理・確認
刈り取った草や木も処分し、仕上がりを依頼者と確認。
よくある失敗として、
他社に依頼した際に「処分費が別料金」と言われて想定以上の出費になった
料金が不透明で見積もりと最終金額が違った
作業範囲が曖昧で、希望した箇所が対応されなかった
黒木開発ではこうした不安を解消するために明確な料金設定と丁寧な説明を重視しており、納得してから依頼できるのが安心ポイントです。
料金が分かりやすく、作業フローもスムーズなのが黒木開発の大きな魅力です。
5.3 選ばれる理由と相談時のメリット
黒木開発が多くの人に選ばれているのは、費用と仕上がりのバランスが優れているからです。利用者の「なるべく費用を抑えたい」という声に寄り添いながら、スピーディーで丁寧な作業を実現しています。
選ばれる理由
低コストとスピードの両立
少数精鋭で無駄を省いた作業により、費用を抑えつつ素早い対応が可能。
柔軟な対応力
機械作業と手作業を現地に合わせて使い分けるため、狭い場所や大きな土地でも安心。
仕上がりの丁寧さ
草刈りや伐採後の処理まできっちり対応するため、依頼者が後処理に悩む心配がない。
相談時のメリット
見積もり・相談が無料
「ちょっと聞いてみたい」段階でも気軽に連絡できる。
専門的なアドバイス
現地を確認した上で、最適な作業内容や費用感を提案してくれる。
安心感のある対応
誠実さを大切にしているため、無理な営業や不要な作業を勧められる心配がない。
よくある失敗として、
業者に依頼したら費用が思ったより高くついた
作業内容が不十分で、結局自分でやり直した
相談しにくく、必要なことを伝えられなかった
といったケースがありますが、黒木開発ではこうした不安を解消できる仕組みが整っています。
「安心して任せられる」という点こそ、黒木開発が選ばれ続ける理由です。
▶︎6. まとめ
6.1 今すぐチェックしておきたい空き家の草刈りポイント
空き家の草刈りを放置するとトラブルや費用増につながります。まずは現状を確認し、管理が必要なポイントを把握することが大事です。チェックリストとしては以下の通りです。
草丈が膝以上になっていないか
隣地や道路への越境がないか
枝やツルが建物や雨どいに触れていないか
虫や害獣の痕跡がないか
行政からの指導や通知がないか
これらを定期的に確認するだけでも、トラブルや修繕費のリスクを大幅に減らせます。草刈りは「見える部分」だけでなく、家全体の安全と資産価値を守る行動です。
6.2 空家の草刈りを定期的に行う心構え
空き家管理で草刈りを続けるためには、習慣化と計画性が重要です。草の成長は早く、放置すれば短期間で管理負担が増えます。心構えとして、以下のポイントを意識すると効果的です。
年に2〜3回の定期スケジュールを設定する
季節ごとの成長スピードを考慮して優先箇所を決める
草刈り作業を分けて負担を軽減する(表側・裏側など)
道具や処分方法をあらかじめ準備して効率化する
体力や距離の問題は業者に依頼して無理をしない
定期的な草刈りは、空き家の安全と資産価値を守る最も簡単で確実な方法です。
▶︎草刈りで空き家の安全と美観を守るなら黒木開発へ
伸びた雑草や放置された木は、防犯や建物劣化のリスクを高めます。黒木開発は現地状況に応じた最適な作業プランで、空き家の管理をしっかりサポートします。
まずは無料見積もりで費用や作業内容を確認。ホームページから簡単にご相談いただけます。
コメント